公的医療保険(国民健康保険、健康保険等)について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
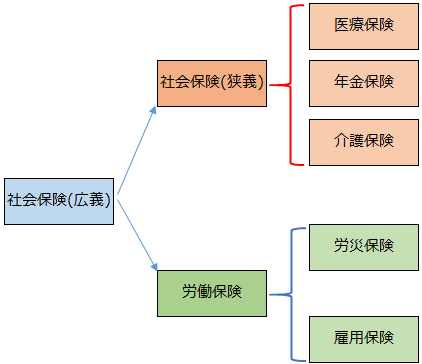
医療保険制度
日本では、民間の生命保険や医療保険に加入していても、すべての者がいずれかの公的医療保険に加入しなければなりません(国民皆保険制度)。
公的医療保険には、「自営業者等が加入する国民健康保険」「会社員等が加入する健康保険(協会けんぽ、組合管掌健康保険)」「75歳以上の者や65歳以上の障害者が加入する後期高齢者医療制度」などがあります。
国民健康保険
保険者
国民健康保険は、「都道府県と市区町村が共同保険者」になるものと、「国民健康保険組合が保険者」になるものがあります。
国民健康保険の対象者
健康保険の対象者(会社員等)とならない自営業者、年金生活者、健康保険の扶養でなくなった人などが、国民健康保険の対象者となります。
なお、国民健康保険については、健康保険とは異なり、被扶養者という制度はありません。
国民健康保険の保険料
国民健康保険の保険料は、「医療分保険料」、「後期高齢者支援金分保険料」、「介護分保険料(40歳以上65歳未満の人に限ります。)」の3つの合計額となります。
国民健康保険の保険料は、所得割や均等割等により計算され、最高限度額が定められています。また、保険料の金額は、市区町村によって異なります。
なお、保険料は前年の所得に基づいて世帯単位で計算され、全額自己負担となります。
【補足】ここも覚える 国民健康保険の保険料は、市区町村ごとに算出方法が異なりますが、一つの世帯に被保険者が複数いる場合は、世帯主が保険料を徴収されます。 |
給付内容
国民健康保険は、療養の給付、出産育児一時金、葬祭費、高額療養費などの給付があります。また、被保険者の業務上の疾病、負傷については、労働者災害補償保険(労災保険)の給付等がある場合を除き、保険給付の対象となります。
なお、健康保険と異なり、原則、傷病手当金と出産手当金の給付はありません。
健康保険とは
健康保険には、「全国健康保険協会が保険者である全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」と「健康保険組合が保険者である組合管掌健康保険(組合健保)」があります。
健康保険の対象者
会社員は、健康保険に加入し、被保険者となります。
被保険者(会社員)により生計を維持されている者で、「年収130万円(60歳以上・障害者は180万円)未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満(配偶者等が同一世帯に属していない場合、被保険者からの援助による収入額より少ない)である」などの要件を満たすのものは、被扶養者としてその保険の適用を受けることができます。
【補足:ここも覚える】 アルバイトやパートの方であっても、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である人は、健康保険の被保険者となります。 なお、4分の3未満であったとしても、次のすべての要件を満たす者は、健康保険の被保険者となります。
|
健康保険の保険料
被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を掛けた金額が、健康保険の保険料となります。
協会けんぽの保険料は、都道府県によって異なり、事業主と被保険者で半分ずつ負担します。これを労使折半といいます。
なお、40歳以上65歳未満の人の保険料には、介護保険料分が上乗せされます。
【補足:ここも覚える】
|
この続きは、
合格セット購入者専用ページにありますテキスト完成版でご確認ください。


.png)